
|
非課税制度を利用するにあたっての手続き方法は、本人確認のための「住民票」や「身体障害者手帳」などの確認書類を用意し、金融機関の支店ごとにその店舗における非課税貯蓄の最高限度額の枠を定めた「非課税貯蓄申告書」を提出するほか、実際に貯蓄するつど「非課税貯蓄申込書」を金融機関等を経由して税務署に提出しなければなりません。
「非課税貯蓄申告書」は2つ以上の金融機関の支店に提出することもできますが、その非課税貯蓄申告書の合計額が350万円を超えることとなる場合には、その超えることとなる非課税貯蓄申告書は提出することはできません。また、一定の預金については、最初に預入れをする際に提出する非課税貯蓄申告書に予定最高限度額を記載した場合には、その後は「申込書」の提出は必要ありません。さらに、間違って限度額を超えて申告すると、新しい「申告書」から順に無効となり、その預貯金は課税扱いになるので注意が必要です。
なお、寡婦年金を受ける人が再婚したり、児童扶養手当を受ける児童の母が子どもの成長に伴ってそれを受けられなくなったときのように、これら非課税貯蓄制度を利用していた人がある時を境に利用できなくなった場合には、その利用できなくなったとき以降に預け入れる預貯金などの利子については非課税になりませんが、それ以前に預け入れたものの利子については引き続き非課税扱いを受けることができます。
現在は低金利のため利息もあまり期待できませんが、今後金利が上向いていく場合もふまえて是非利用したい制度です。
図36 利子非課税制度と必要書類
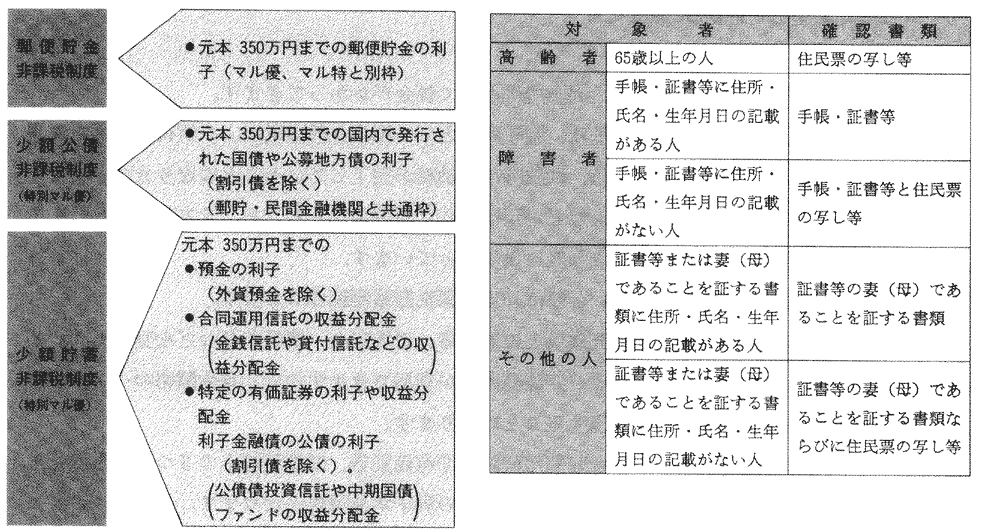
前ページ 目次へ 次ページ
|

|